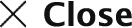境界知能のお子さんの高校の選び方
軽度な知的障がいと平均知能指数とのはざまに位置する、境界知能のお子さんは、病気でも障がい者という位置づけでないものの、学習の遅れや集団行動が苦手などの特性を持っています。そういったお子さんの高校選びについて紹介していきます。
- 境界知能のお子さんには、学習支援が充実した公立・私立高校や通信制高校が選択肢となってくる
- 技能連携校では、個別対応や実技中心の授業で安心して学べる
- 興学社高等学院では、WISC検査やSSTを活用し、生徒の特性に寄り添う柔軟な教育を提供
高校選びのポイント
通常の公立・私立高校
境界知能の生徒が公立・私立高校を選ぶ際には、学習支援の充実度が重要です。一部の学校では、特別支援教育コーディネーターが在籍し、必要なサポートを提供している場合があります。また、通級指導を活用できる学校もあり、個別の支援を受けながら学習を進められます。ただし、通常の学習カリキュラムに適応する必要があるため、学習のペースやサポート体制を事前に確認することが大切です。
通信制高校
通信制高校は、自宅で学習を進められるスタイルの学校です。登校日が少なく、自分のペースで勉強ができるため、境界知能の生徒にとって学びやすい環境といえます。課題の提出やレポート学習が中心ですが、スクーリング(対面授業)や個別サポートがある学校もあります。サポート校と連携している通信制高校なら、対面での学習支援を受けることも可能です。学校ごとに支援体制が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
通信制高校を卒業するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
要件1:3年以上在籍すること
通信制高校は、学校教育法により「3年以上在籍すること」が卒業の必須条件とされています。多くの通信制高校では単位制を採用しており、1年間で修得できる単位数には上限があります。そのため、仮に1・2年次で多くの単位を取得したとしても、3年間在籍しなければ卒業することはできません。
要件2:74単位以上を修得すること
卒業までに、必履修科目を含めて74単位以上を修得する必要があります。単位は「自主学習 → レポート提出 → スクーリング → テスト」の流れで取得します。まず、教材を使って自主学習を行い、レポートを作成・提出。添削後に復習を行い、登校日に教師の指導を受けるスクーリングに参加します。最後に、学科ごとの試験に合格することで単位が認定されます。
要件3:30単位以上の特別活動に参加すること
通信制高校では、ホームルームや文化祭、清掃活動、体験学習、校外学習など、30単位以上の「特別活動」への参加も卒業要件に含まれます。これらの活動はスクーリングと併せて実施されることが多く、学校によって内容が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
高等専修学校
高等専修学校は、中学校卒業者を対象に実践的な職業教育を行う後期中等教育機関です。通学期間は1~3年で、3年間学ぶと高等学校卒業資格を取得できます。情報・医療福祉・美容・工業など多彩な分野を学べ、専門学校への進学も可能です。不登校経験のある生徒や特性を持つ生徒も多く、個性を尊重した教育が特徴です。軽度知的障がいや境界知能のお子さんは、学校側と相談し、特別な配慮の有無や学習環境を確認することが大切です。
境界知能のお子さんなら、技能連携校がおすすめ
技能連携校は、発達障がいや知的障がい、境界知能のあるお子さんにとって相性の良い学びの場です。最大の特長は、一人ひとりの特性や学習スタイルに合わせた柔軟な指導が行えること。集団授業が苦手でも、少人数や個別対応で安心して学ぶことができます。
カリキュラムには実技中心の授業が多く、「じっと座っているのがつらい」「座学よりも手を動かすほうが得意」というタイプのお子さんにも向いています。こうした環境では「わかる」「できた」という成功体験を積みやすく、自己肯定感を取り戻すきっかけにもなります。不登校の経験がある場合や、対人関係に不安を抱えるお子さんにとっても、安心して通える居場所としての役割を果たしてくれるのが技能連携校なのです。
通信制高校・技能連携校
【技能連携校】
興学社高等学院
98.9%

無理をさせずに得意を伸ばしてくれる学校
WISC-Ⅳ検査でお子さんの特性を把握し、得意を伸ばせる教育を行う
興学社高等学院は、境界知能も子どもの個性の一つとして捉えており、入学の際に療育手帳の有無は問わないため、境界知能をお持ちのお子さんでも全日制高校のような生活を送ることができます。希望者に対しては、「WISC-Ⅳ検査」と呼ばれる発達のバランスを知れる検査を実施し、生徒の個性に合わせたサポートを行うため、お子さんに無理をさせることなく、楽しい学校生活を送ることができる環境といえるでしょう。
コミュニケーションに関する苦手を克服できる
興学社高等学院は、SST(ソーシャルスキル・トレーニング)と呼ばれる、社会に出た時に役立つ、コミュニケーションスキルを学ぶ授業を取り入れているため、対人コミュニケーションが苦手なお子さんも安心できる環境です。一つの方針を強制する教育ではなく、生徒一人ひとりの多様性を認めてくれる学校といえるでしょう。
▼千葉県の新松戸校はコチラ▼
▼埼玉県の新越谷校はコチラ▼
総合進学科は、国語や数学、英語といった高校生の必修科目のほか、ハンドベルやフォトのように、特色のある授業を選べる学科です。授業の種類は160種類以上(2023年4月調査時点)あり、興味がある分野を見つけるきっかけにもなるでしょう。中にはオフィスソフトなど、就職した際に、すぐに役立つスキルが身に付く授業も用意されています。
リベラルアーツ科では、お子さんが持つ特有の感覚を社会で活用できるように、コントロールしていく力を身につけます。応用行動分析(ABA)を通して、人間の行動のきっかけを考え、自分が望む結果を得るためには、どう行動することが望ましいのか導けるよう、トレーニングを実施します。
▼千葉県の新松戸校はコチラ▼
▼埼玉県の新越谷校はコチラ▼
嬉しかった
興学社高等学院に入学してから、私は勉強に力が入りました。また、将来に向けての考え方をしっかりと考えることもできました。 私は、性差別に人一倍敏感なジェンダーレスです。自分自身がスカートをはくこともあります。多様性を認めてくれるこの学校に入学できたことをとても嬉しく思っています。
概念を覆してくれる
興学社高等学院は穏やかでとても楽しいところです。 前の学校では「みんなに合わせなきゃ」とか思っていたけど、この学校は良い意味でマイペースでいられる場所です。 「学校=辛い場所」という考えを覆す学校だと私は思います!
登校できた
興学社高等学院に通えて本当に良かったと親子で思っております。先生方は、とても親身に接してくれ、身体の不調もあり毎日登校はできませんでしたが、遅刻(午後から)登校でも明るく元気に迎えてくれた先生方に感謝しております。
紹介動画
▼千葉県の新松戸校はコチラ▼
▼埼玉県の新越谷校はコチラ▼
| キャンパスの所在地 | 【新越谷校】埼玉県越谷市南越谷1-15-1 6F 【新松戸校】千葉県松戸市新松戸4-35 |
|---|---|
| アクセス | 【新越谷校】新越谷駅・南越谷駅から徒歩5分 【新松戸校】新松戸駅・幸谷駅から徒歩2分 |
| 電話番号 | 047-309-8181 |
学校選びで大切なステップ
1.事前リサーチ
まずは、気になる学校の公式サイトやパンフレットを確認し、支援体制やカリキュラムの内容を把握しましょう。特別支援の有無や、学習サポートの充実度、授業の進め方などをチェックすることが大切です。また、学費や通学のしやすさなど、実際に通う際の条件も考慮しておくと安心です。
口コミサイトやSNS、在校生・卒業生の体験談を参考にすることで、学校の実際の雰囲気や指導の特徴を知ることができます。可能であれば、保護者の意見や経験も確認し、多方面から情報を集めると良いでしょう。
2.体験入学・学校見学
実際に学校を訪れ、授業の雰囲気やサポート体制を確認することはとても重要です。オープンキャンパスや個別相談会を活用し、教師や在校生と直接話すことで、支援の具体的な内容や先生の対応を詳しく知ることができます。また、学習環境や校内の設備が本人に合っているか、落ち着いて学べる環境が整っているかも確認しましょう。特に、支援が必要なお子さんの場合、クラスの雰囲気やサポートスタッフの対応が本人に合っているかをしっかり見極めることが大切です。体験授業に参加できる場合は、実際の授業を体感し、学びやすさをチェックしてください。
3.専門家や支援機関への相談
学校選びに悩んだ際は、教育相談センターや発達支援機関などの専門家に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。境界知能の特性を理解した上で、どのような環境が適しているかを専門的な視点から提案してもらえるため、より確実な選択ができるようになります。特別支援教育に詳しいカウンセラーや学校関係者に意見を聞くことで、本人に合った進路を見つけるヒントを得られます。場合によっては、福祉サービスや支援制度についての情報も提供してもらえるため、将来の選択肢を広げることにもつながります。
境界知能のお子さんに関する相談先
地域の相談機関
まずは、普段から利用している「かかりつけの小児科医」に相談してみましょう。小児科医は発達障がいや知能障がいなど、子どもの発達に関する豊富な知識を持っています。小児科医を通して、アドバイスや地域の支援機関を紹介してもらうこともできるので、相談して頼ってみましょう。
また、自治体の「児童相談所」でも18歳未満の子どもに関する相談を受け付けています。児童福祉司や児童心理司といった専門知識を持つスタッフが在籍しているので、相談されたい場合はお近くの自治体の窓口へ連絡してください。
児童発達支援センター
児童発達支援は、障がいのあるお子さんの特性に合わせて日常生活や社会生活を営むサポートをしている施設です。利用するには自治体の障がい福祉窓口を通すことになりますが、お子さんが将来自立するのに必要な技能や知識、日常生活に必要な基本動作などの専門的な訓練ができます。
まとめ
境界知能のお子さんは、努力をしていてもなかなか学校や日常生活で周りに認められないことが多く、自信喪失や非行などに陥りやすい傾向があります。お子さんのやる気を向上されるためにも、気がかりな行動が見られたら、早めに専門家へ相談して、周囲の支援を得ることが大切です。
進学を考える際には、境界知能であることを本人や保護者が確認したうえで、学習支援があったり楽しいスクールライフが過ごせる環境が整っている学校を選ぶようにしましょう。
不安な事は家庭で抱え込まずに、専門機関の窓口に相談してみるといいでしょう。
目的や特徴から選ぶ!
おすすめの通信制高校
・技能連携校
通信制高校は、学校によって力を入れている分野や強みが異なります。
ここでは、学校に求めるサポート体制や通信制高校に入学する目的別でおすすめの通信制高校を紹介しているので、
自分自身やお子さんの個性、希望の進路に合った通信制高校を選びましょう。