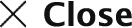発達障がい・グレーゾーンのお子さんが不登校になる原因とは?
発達障がい・グレーゾーンの特性を周りに理解してくれずにお子さんが不登校になることがあります。こちらでは、各発達障がいの症状の特性や不登校になり得る原因などを紹介していきます。また、もしお子さんが不登校になった場合にどのように対応すればよいかなどもまとめているので参考にしてください。
発達障がい・グレーゾーンのお子さんの特長とは
ADHD(不注意・多動・衝動性)
ADHDは、「不注意」「多動性」「衝動性」という3つの症状がみられる発達障害のひとつです。
「不注意」の特性が強いお子さんの場合は、授業中に集中力が続かなかったり、宿題や忘れ物が多い、ケアレスミスが多いなどの特性が見られます。
「多動性」の特性を持つお子さんは、落ち着きがなくじっとしていられないために教室内を歩き回ったり、同じ作業を取り組むことができないなどの行動が目立ちます。
「衝動性」の特性が強い場合は、思いつきで即行動に移したり、人の話をさえぎったり、順番を待てないなどの行動があります。ADHDの方全体に言える傾向として、感情をコントロールするのが難しい方が多いようです。ADHDは、どれかひとつの行動が強いお子さんもいれば混合型のお子さんもおり、適切な支援をするためにも専門医に診断してもらった方が良いでしょう。
ASD(自閉症スペクトラム・アスペルガー)
ASDは、「興味や行動の偏り」や「人間関係の構築が苦手」とする特性を持つ発達障がいのひとつです。
具体的な特性として、人の目をあまり見ない、他人に興味がない、言葉が遅い、マイペースで物事を進める、興味のある事柄に深くのめりこんだり、一定の行動に強いこだわりを持ち柔軟に対応できないなどで、聴覚や視覚が過敏な方もいます。人との交流が苦手で興味がないために、学校での集団行動や人間関係で苦労するケースが多いのが特長です。
就学後、対人関係で問題を抱えて不安定になるお子さんもいますが、適切な支援を受けて自分の特性を受け入れれば落ち着いて得意な分野を仕事に活かす方もいます。
LD(学習障害)
LDは知的能力には問題はないものの「読み」「書き」「計算」などの特定の学習に困難をきたす状態で、小学生になったタイミングで周囲に気づかれることが多いです。
例えば読字障害(ディスレクシア)の特性を持つお子さんは、文字を読むことが困難ですが、同じ内容を耳から聞くヒヤリングでは理解できるケースもあります。
計算障害(ディスカリキュリア)の特性のお子さんは、数学の概念がうまくつかめない、数値を覚えるのに苦労するなどの症状が見られます。
書字障害(ディスグラフィア)の特性の方は、「てにをは」を使いこなせなかったり、鏡文字になってしまう、文字の大きさを揃えて書けないなどの症状があります。
これらの症状は、本人が頑張っても“できない”事柄のため、授業についていけないと感じて自己肯定感が低下することがあります。そのため、周囲が理解してそれぞれの特性を工夫して乗り越える方法やサポートを提供してあげることが大切です。
発達障がい・グレーゾーンの不登校の原因は?
学校環境に適応しにくい
まずASD(自閉症スペクトラム・アスペルガー)の特性が強いお子さんの場合、他人に興味がなかったり、人の目を見るのが苦手であることが多いので、人間関係の構築が難しい点があります。また、感覚過敏の特性を持つケースもあるため、クラス内の雑音が過度に気になって気分が悪くなることもあるため、集団行動が難しくて不登校になるケースもあります。
そして、ADHD(注意欠如・多動性障害)の特性が強いお子さんの場合は、感情のコントロールが苦手だったり順番を待つことができない、人の話を遮るなど人間関係でトラブルを起こすことが多いため、少しずつ孤立していき不登校になるケースがあります。
学習の遅れ
発達障がいの特性を持つお子さんの中には、学習の遅れが目立つ方もいます。特にLD(学習障害)の特性が強いお子さんは読む・書く・計算するという特定の学習行為が難しいために成績を向上させるのが難しく、学校で授業を受けることにストレスと感じることになります。本人を含めて周囲がLDであることに気づかなければ、適切なサポートを受けられず劣等感を抱いて不登校になってしまいがちです。
ASDの 特性が強いお子さんは、興味のある授業以外は成績が良くないことがあったり、ADHDのお子さんは集中力が持続しないために、やはり成績につながらない傾向があります。
学校で孤立してしまったり、周囲の理解不足が原因のケース
ASDやADHDの 特性が強いお子さんは、他人の気持ちになって考えることや共感することのが苦手な方も多く、本人に悪気がなくてもトラブルを起こしてクラスに馴染めないケースがあります。
また、たとえ教師が「発達障がい」という特性を抱えていると認識していたとしても、クラスメイトがきちんと理解してくれるケースは少なく、同調圧力の傾向が強い日本では「変わった子」というレッテルを貼られると孤立したりいじめの対象になってしまうケースも多くあり、その結果不登校になってしまう子もいます。
発達障がいの子どもが不登校になった場合の対応は?
無理に学校に登校させない
お子さんが不登校になったら、無理やり学校に登校させようと強要するのはやめてください。お子さんなりに頑張った結果、強いストレスを抱えこんで「学校に行けない」「行きたくない」という流れになったわけですから、ここで無理に学校へ行かせようとすると、さらなるストレスを抱え込み、鬱になるなど二次的な問題に発展する可能性もあります。
親御さんからすると、学校を休むことで「勉強が遅れる」「内申書が心配」などの心配があるかもしれませんが、まずは安全なお家でゆっくりと休息させてあげることが大事です。学校を休むことへの罪悪感を抱かないように、声かけなどもしてください。
家を「安全」だと認識してもらえるようにする
発達障がいの特性を抱えるお子さんは、感情や思っていることを言葉で表現するのがうまくありません。お子さんが何かを話そうと言う兆しが見えたら、否定や批判をせずに時間をかけてじっくりと話しを聞いてあげましょう。
ただし、無理やり聞き出そうとするのはNGです。お子さんの不安を早く解消させたい気持ちはわかりますが、親御さんが焦るとお子さんも不安定な気持ちになって精神的に追い詰められてしまうことも。まずは、家の中は居心地が良くて安全であると認識してもらうことから始めましょう。
学校と連携する
お子さんが不登校になったら、学校側と連携をとることも大切です。最近ではスクールカウンセラーが在籍している学校も増えているため、担任やスクールカウンセラーとで不登校中の学習の進め方やその他のサポート、出席数の確認、学校外の公的福祉支援を紹介など相談をしてみましょう。
ただし、お子さんが復学したいという気持ちになっていない状態時に先走ることは望ましくありません。
学校と連携を取りつつも、お子さんの意思を尊重して情報を集めてください。
医療機関やフリースクールなどを活用する
発達障がいのお子さんが不登校になったら、かかりつけの医師に相談するのもひとつの方法です。相談することで、お子さんの今の精神状態を把握することができますし、適切な相談機関を教えてくれるからです。
また、お子さんが少しずつ落ち着いてきたら、元の学校へ復学する道だけでなく、フリースクールや教育支援センターなどへの通学、家庭教師の派遣などさまざまな可能性があることを示唆してあげましょう。
まとめ
発達障がい・グレーゾーンの特性を持つお子さんが不登校になった場合、不登校までの課程や理由があるはずです。すでにお子さんは大きなストレスをため込んでいる可能性が高いため、無理に登校させようとしたり批判することはしないで、お子さんに寄り添うことが何よりも重要です。
不登校によって親御さん自身も不安を抱えることになると思いますが、その不安をお子さんに押し付けることはしないで、まずはお子さんのストレスが和らぐまで居心地の良い環境を提供してください。
お子さんが落ち着いてきたら、次のステップをお子さんと一緒に考えていきましょう。
発達障がいへのサポート体制が充実!
先に技能連携校や通信制高校を見る
目的や特徴から選ぶ!
おすすめの通信制高校
・技能連携校
通信制高校は、学校によって力を入れている分野や強みが異なります。
ここでは、学校に求めるサポート体制や通信制高校に入学する目的別でおすすめの通信制高校を紹介しているので、
自分自身やお子さんの個性、希望の進路に合った通信制高校を選びましょう。